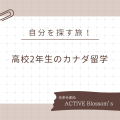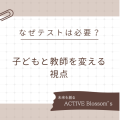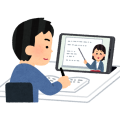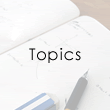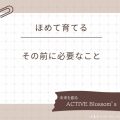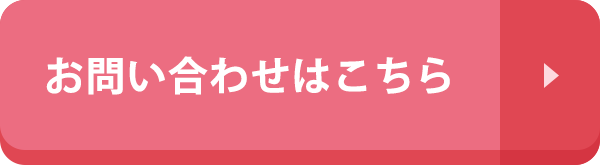提出物と9教科テスト、子どもたちの負担を考える ~テストを見直す③~
これまで、「だれのためのテストか」「どうあるべきか」というお話をしてきました。
今日は、テストのやり方について考えてみます。
多くの中学校では前期・後期があり、それぞれに中間テストと期末テストがあります。
つまり、おおむね3か月に1回テストがあるということになります。
これだけでも大変で大きなストレスになりますが、さらに問題なのは、1日、あるいは2日で多くの教科のテストを受けなければならないことです。
これは本当に大変です。
私たちもそのようにテストを受けてきたので「当然のこと」と感じがちですが、冷静に考えれば非常に負担の大きい仕組みです。
受けるだけでなく、それぞれの教科の勉強を事前にしなければならず、さらに提出物もあるため、子どもたちは本当に大変なのです。
中間テストは国語・数学・理科・社会・英語の5教科。
期末テストはそれに加え、音楽・美術・技術家庭科・体育を含めた9教科になります。
まさに「テストのために毎日学習している」と言っても過言ではありません。
しかし、本来「学ぶ」とは、興味や関心のあることに対して、
自分の知識や理解を最大限に活用し、納得するまで取り組むことだと私は思います。
「テストで300点を取るため」という目的で学習するのは、本質から外れているのではないでしょうか。
そこで提案します。
-
教科の評価は、日常の歩み(レポート、単元テスト、ノートなど)で行う。
-
安易にまとめてテストをするのではなく、必要であれば教科ごとに日を分けて実施する。
いかがでしょうか。
日常の学習が「テストのため」ではなく、本当に子どもたち自身のものになっていく必要があります。
そうすれば、学校は楽しく、そして将来の自分にとっても大切な場所になるはずです。