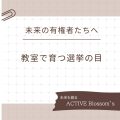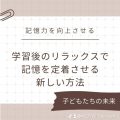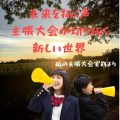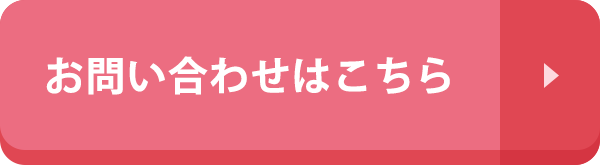先週金曜日は、青少年育成推進員として地域のつどいに参加しました。
講演会では、警察署の方から青少年の闇バイト問題についてお話がありました。
地域の現状を丁寧に説明していただき、
「みなさんで温かく見守っていきましょう」というメッセージが印象的でした。
その後はグループディスカッションです。
私のグループには高校の校長先生、保育園の園長、教育委員会の先生、小学校のPTA会長、中学校のPTA役員など、さまざまな立場の方が参加していました。
議題は主に高校生・中学生のスマホ事情でした。
今や高校生は100%、中学生もほぼ100%がスマホを所有しています。
便利な半面、詐欺やいじめ、スマホ依存などのリスクも指摘されました。
禁止一辺倒ではなく、「どう活用するか」が大切だという意見で一致しました。
一方で、ある保護者からは「うちの息子は部活や勉強で忙しく、スマホをいじる暇がない」という声もありました。
そこから、「子どもが夢中になれることを持つこと」「やるべきことに一生懸命取り組む姿勢を育むこと」が最も大事だという話題に発展しました。
さらに大切なのは、大人自身がやりたいことや、
やらねばならないことに生き生きと取り組む姿を示すことです。
親も先生も、地域の大人すべてが情熱を持って行動し、その背中を見せることが、
結局は子どもの育成につながる――そんな結論に至りました。
「子は親の鏡」
「大人が変われば、子どもも変わる」
本当に大切な教訓を得られた一日でした。
この話には続きがあります。
最後のまとめで、教育長の少し長い話がありました。
子どもたちの現状を話し、多様性が認められるこの時代、
制服の自由化、何も制服でなくてもユニクロでもいいのではないか、
学校選択制については、どこの学校で学んでもいいんじゃないか、
最近インスタをはじめ、若い人に教えてもらいながら取り組んでいるなどのお話です。
SNSは欠かすことのできないもの、それについて私たちも知らなければならない、という話です。
このつどいの話とは、違います。
私たちが考えなければならないのは、
目の前にある問題に対して、どうすればいいか、何をすればいいかではなく、
学校で何を学べばいいのか、どんなやりがいをもつのか、
そして、生きがいをどう持たせていくかです。
そのために親がが、どうあるべきかです。
この現代社会の問題に、どう大人が立ち向かっていくか、
その姿こそが、青少年健全育成の特効薬になると、私は思います。